国内の事業者が事業者向け電気通信利用役務の提供を受けた際の経理処理
最近、お客様への訪問時に立て続けて話題にのぼった「事業者向け電気通信利用役務の提供」について考えました(この内容では、国内の事業者が電気通信利用役務の提供を受けた場合を想定しております。)。普段経理処理を担当されている方でもあまり聞き慣れない言葉だと思います。
電気通信利用役務の提供とは、電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われるサービスの事をいいます。具体例としては、
・インターネット等を通じて行われる電子書籍・電子新聞・音楽・映像・ソフトウエア(ゲームなどの様々なアプリケーションを含みます。)の配信
・顧客に、クラウド上のソフトウエアやデータベースを利用させるサービス
・顧客に、クラウド上で顧客の電子データの保存を行う場所の提供を行うサービス
・インターネット等を通じた広告の配信・掲載
・インターネット上のショッピングサイト・オークションサイトを利用させるサービス(商品の掲載料金等)
・インターネットを介して行う宿泊予約、飲食店予約サイト(宿泊施設、飲食店等を経営する事業者から掲載料等を徴するもの) など ※ 国税庁HPより一部抜粋
上記のような取引で、サービスを受ける者が通常事業者に限られるものが事業者向け電気通信利用役務の提供となります。如何でしょうか?普段の経理処理の中でも意外と思いあたる内容がございませんか?正しく処理を行うためにも、以下を意識していただけますとより良い処理に資するかと思います。
経理のご担当として実務を行う方は、先ずは請求書や領収書などの証憑でしっかりと「どこの会社から」「何のサービスを受けたのか」の内容の把握を行いましょう。特にメール添付やブラウザからダウンロードするもの等、電気通信利用役務の提供に関しては紙媒体のケースは少ないため注意が必要です。外国語であったり、請求内容が不明確なものについては、翻訳ソフトを使ったり、自社内の取引担当者に直接確認することが有効です。インボイス制度が始まって以降、証憑の収集に関しては常日頃から意識されているかと思いますのでこの辺りは通常の業務と変わりません。
次に会計システムにて処理を行う上では、多くの会計システムでは「特定課税仕入れ」という消費税の課税区分が用意されております。そちらにて処理を行うと、その他の海外事業者に向けた支払取引とは明確に分けて処理することが可能になるかと思います。
より詳しい内容は国税庁の「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm等や、関連のパンフレットをご参照下さい。


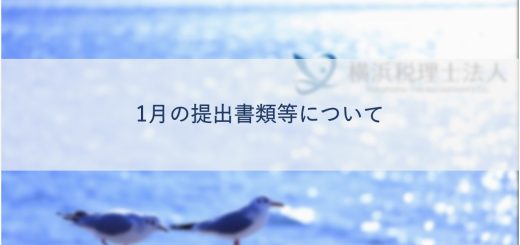
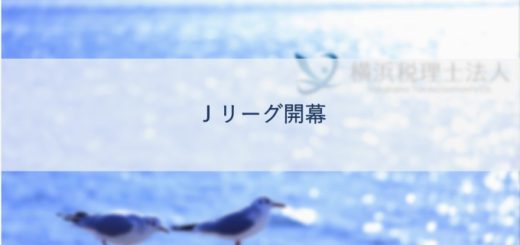
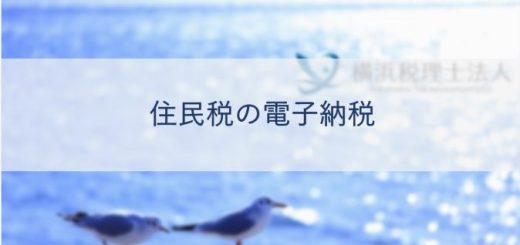
最近のコメント