税務署による「法定調書の監査」とは?
会社経営者にとって、「税務署からの連絡」は少なからず緊張するものですよね。法人税等の税金に関する「税務調査」は有名ですが、実は税務署が行う調査には「法定調書の監査(法定監査)」というものも存在します。
この法定監査は,税務職員等の質問検査権に基づき行われるものですが、「法定監査」はあくまでも税務署による呼称であって、正式な名称ではないのですが、実務上はそう呼ばれています。
そして、この法定監査は年間の実施件数が極端に少なく、非常にレアな調査になるので、経験のある税理士事務所はそう多くないと思います。
今回は、レアな法定調書の監査について基本的な内容を確認しつつ、税務調査との違いについても触れてみたいと思います。
◆法定調書とは何か?
法定調書とは、税務署に提出が義務づけられている各種支払調書のことを指します。代表的なものとしては以下が挙げられます。
・給与支払報告書や源泉徴収票
・報酬・料金、契約金及び賞金の支払調書
・不動産の使用料や売買に関する支払調書
これらは、税務署が個人や法人の所得を把握するための重要な資料となり、毎年1月末までに税務署へ提出することが求められています。
◆法定調書の監査とは?
税務署は、提出された法定調書が正しく作成・提出されているかを確認するために「法定調書合計表」等を確認し、必要に応じて調査(監査)を行います。これが「法定監査」と呼ばれます。
監査の目的は、
・法定調書が正しく提出されているか
・記載内容に誤りや漏れがないか
・実際の支払内容と調書の内容に齟齬がないか
を確認することにあります。 法定監査では、契約書や請求書等により各種支払の内容を確認したり、法定調書の内容を基礎資料と突合したりします。必要に応じて事業者に説明や追加の証憑書類の提示を求めることもあります。
◆税務調査との違い
法定監査は法人税等の税務調査と混同されがちですが、両者には違いがあります。
・調査対象
法定監査は、提出された「法定調書合計表」「支払調書」「源泉徴収票」などの帳票が対象です。一方、税務調査は法人税、所得税、消費税など事業全般の経理処理・税金申告内容を対象としています。
・調査の範囲・内容
法定監査は、あくまで調書の記載内容が正確かどうかを確認する限定的な調査です。そのため調査の結果、提出調書の記載事項に誤りや、提出漏れ等があった場合であっても、正しい法定調書の提出をすればよく、追加納税等の処分を受けることはありません。あくまで、過去分のチェックを通じて今後のミスを減らしていくというスタンスであるということです。
そして、法定監査は、資料や帳票を提出して説明する程度で済む場合もあれば、1日程度調査官が会社を訪問し資料等を全般的に確認する場合もあります。
一方、税務調査は、売上や経費、在庫などの会計処理、税務処理について全般的に確認を行い、申告漏れや脱税の有無を確認する網羅的な調査となります。その為、調査は数日間に渡って調査官が会社を訪れ、帳簿・証憑書類・契約書など幅広く細かく確認されます。もしも申告誤り等の指摘事項が生じた場合には、申告書の修正に加え、追加納税・加算税等が課されることになります。
◆誤りがあった場合、税務調査に移行することはあるのか?
通常であれば、「法定監査」から法人税・源泉所得税等の「税務調査」に移行することはないとされています。
ただし、源泉徴収漏れ等が判明した場合には、適切に源泉徴収するように“指導”されることはあります。その場合、あくまでも税務調査ではないので、自主的に追加納付すれば、加算税等の罰則が課されることはありません。
しかしながら、極端に源泉徴収漏れが多い等の実態が判明した場合には、通常の税務調査に移行するケースも想定されます。その場合には、別途、税務調査に係る調査事前通知がなされることになりますので、法定監査から直ちに税務調査に移るということはありません。
◆法定監査への対応ポイント
・正確な調書作成と期限内提出
税務署が最も重視するのは、記載漏れや誤記がないかということです。支払額・マイナンバー・住所・氏名など適切に確認し、細かい部分まで正しく記入しましょう。
・根拠資料の保存
支払った金額が確認できる請求書や振込明細を整理しておくことが大切です。国税関係書類は通常7年間の保存が求められていますので、税務署は根拠資料がある前提で法定調査に来ます。
・誠実な対応
税務署から確認を求められた場合には、誠実に説明し必要な資料を提示することで、監査もスムーズに終わるはずです。調査官も「人」なので、極端に冷たい態度をとってしまうと、それ相応のリターンがあるかもしれません。。。
◆まとめ
法定監査は、事業者にとっては「税務署の調査」という点で身構えてしまいがちですが、実際には帳票の整合性を確認する比較的限定的なものです。日頃から正確に調書を作成し、根拠資料を整理しておくことが、不要なトラブルを避ける最善の方法です。税務署からの監査連絡が来たとしても、慌てず冷静に対応できるよう、普段から準備を整えておきましょう。
横浜税理士法人
服部彰男


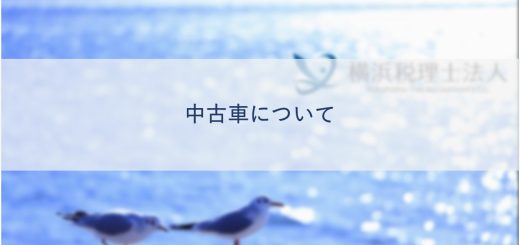
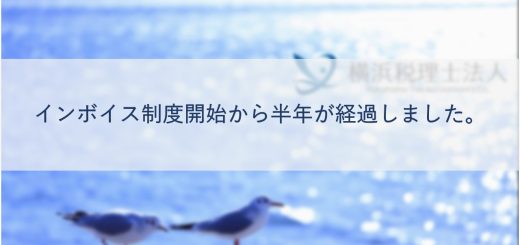
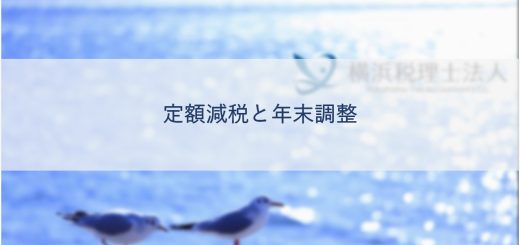
最近のコメント