中古車について
近年、最新の安全運転支援システムなど便利なシステムが付いている車が多くなっているかと思います。ハイブリッド車、電気自動車なども増えてきています。
そんな時代の中ですが、私は昔から好きな中古のマニュアル車を購入しました。もちろんガソリン車です。購入した車は、ホンダのインテグラタイプRの2005年式です。カラーはチャンピオンシップホワイトでシートが赤のレカロシートで当時ホンダでは人気があった組合せだと思います。
販売店は私の自宅から遠いところにありますが、ホンダのスポーツカーに特化している販売店で購入しました。整備の技術が優れているところです。20年前の車ですので入手困難な部品などもありますが、この販売店はかなりの部品を確保していまして、安心できる販売店です。購入の相談・商談は遠方のため電話で行いました。従業員の方は数十名いるかと思いますが、社長さん自らが対応してくれました。車の細かい状態の説明や写真なども送っていただき、信頼できる販売店そして社長さんと思い、購入することに決めました。納車では社長さんが陸送で運んできてくれて、車の話で盛り上がりました。今でも社長さんには気兼ねなく車の相談をしています。
ここ数年、新車の価額がかなり上がったと思います。もちろんハイブリッド車、電気自動車そして安全支援システムや物価高も価額高騰に影響していると思います。法人も社有車、営業車などとして乗用車、トラックなどの中古車を購入していることもあるかと思います。
事業の用に供していれば、減価償却費として経費にすることができます。中古資産の減価償却耐用年数について説明したいと思います。
中古資産を取得して事業の用に供した場合には、その資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。また、使用可能期間の見積りが困難であるときは、簡便法により算定した年数によることができます。ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額をいいます。)の50パーセントに相当する金額を超える場合には、使用可能期間の見積りや簡便法による耐用年数の算定をすることはできず、法定耐用年数を適用することになります。
簡便法による耐用年数の算定方法は、次のとおりです。
- 法定耐用年数の全部を経過した資産
その法定耐用年数の20パーセントに相当する年数 - 法定耐用年数の一部を経過した資産
その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20パーセントに相当する年数を加えた年数
なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。
(注)中古資産の耐用年数の算定は、その中古資産を事業の用に供した事業年度においてすることができるものですから、その事業年度において耐用年数の算定をしなかったときは、その後の事業年度において耐用年数の算定をすることはできません。
(根拠法令等 耐令3、耐通1-5-1~4)


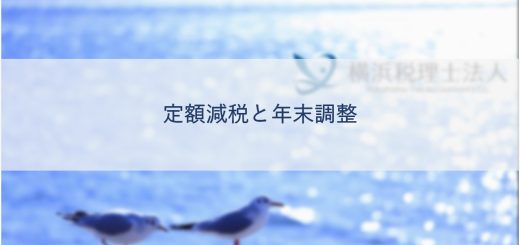
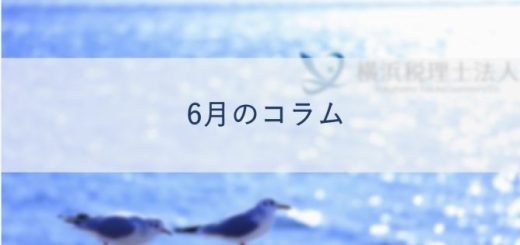
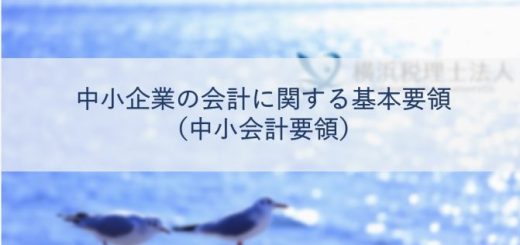
最近のコメント